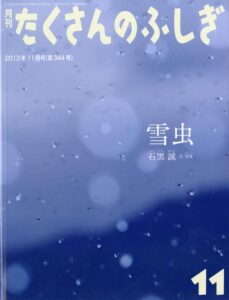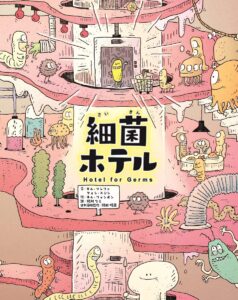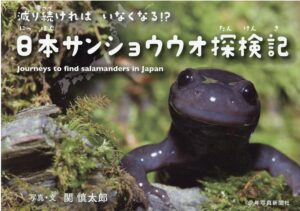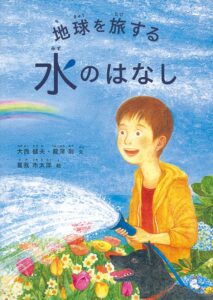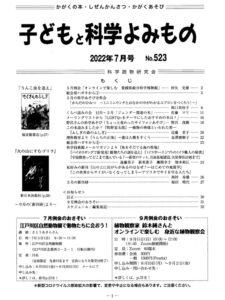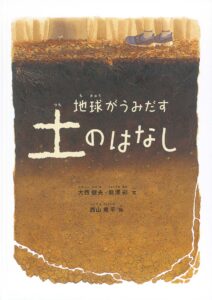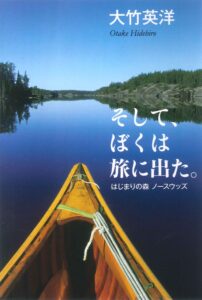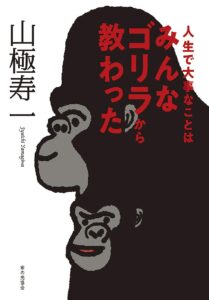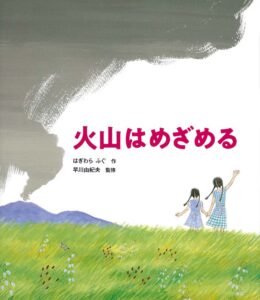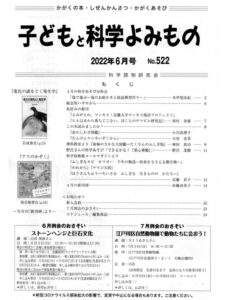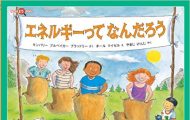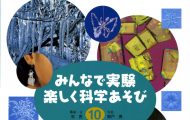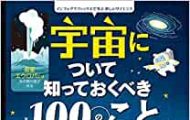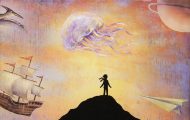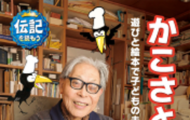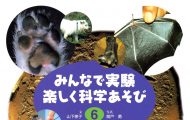- Home
- 過去の記事一覧
本や記事を検索
カテゴリー
科学読物ピックアップ
-
『子どもに教えたい大人も知っておきたい 世界を変えた建物』(エクスナレッジ、2013)
-
『ビジュアル探検図鑑 小惑星・隕石 46億年の石』(岩崎書店、2023年)
-
『宇宙ステーションにかけた夢』(くもん出版、2006)
-
『からだであそぼう かた』(ポプラ社、2005)
-
『宇宙について知っておくべき100のこと』(小学館、2017)
-
『相対性理論の式を導いてみよう、そして人に話そう』(ベレ出版、2011)
-
『ハクチョウ』(アリス館、2007年)
-
『そして、ぼくは旅に出た。はじまりの森ノースウッズ』(あすなろ書房、2017年)
-
『大きな大きなせかい』(偕成社、1996)
-
『紙飛行機を飛ばそう』(さ・え・ら書房、1986)
科学読物研究会|Japanese Society of Science Books for Children
科学読物研究会は、1968年に故吉村証子のよびかけで発足しました。私たちは、すべての子どもたちに科学の本に親しんでもらうために、科学の本の研究、普及、創作に努力したいと思っています。
科学読物研究会は、1968年に故吉村証子のよびかけで発足しました。私たちは、すべての子どもたちに科学の本に親しんでもらうために、科学の本の研究、普及、創作に努力したいと思っています。
発足当時は、子どものための科学の本がまだまだ少ない時期でしたが、良い科学の本を作りたい、読みたい、楽しみたいという仲間は全国にひろがり、それととも に科学の本もたくさん出版されるようになってきました。現在、会員は全国に約 300 人います。
でも最近、科学の本が売れない、図書館でも手にとってもらえない、と声を聞きます。それは、どんな本があるか、どんな内容の本なのかわからないとか、手に取ってもらいにくいということがあると思います。
科学読物研究会のホームページでは、こんな分野のこんな本がおもしろいですよと、アクセスした人が本を読みたくなるような情報を提供する「科学の本の情報貯金箱」を目指しています。どなたでもご協力を お願い致します。
Copyright © 科学読物研究会|Japanese Society of Science Books for Children All Rights Reserved.