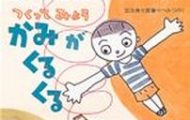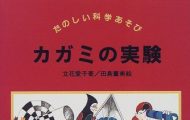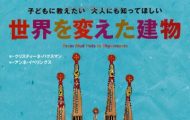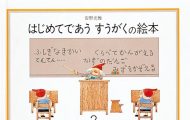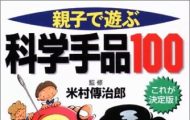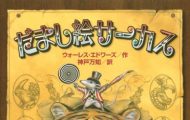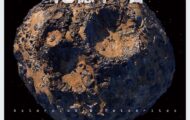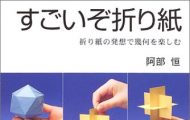会則
1. この会は「科学読物研究会」とよぶ。
2. この会は科学読物の研究をおこなうことによって、子どもたちの科学読物および科学する心の向上と普及に役立つことを目的とする。
3. この会は、この目的をはたすために、つぎの活動をおこなう。
(ア) 例会と分科会を定期的にひらく。
(イ) 会報を発行し、研究成果の発表と会員の交流の場とする。
(ウ) そのほか、目的に沿った活動(講座や研究発表、全国交流会)をおこなう。
4. この会には、科学読物に関心をもつひとはだれでも入会でき、その年度の会費を添えて入会を申し込んだ人が会員である。
5. この会の運営費用は、会費を基本とし、活動を行うための寄付や研究助成をうけることができる。会費は年会費とし、その金額は別に決める。
6. この会の最高機関は総会である。総会は、運営委員会が年一回ひらく。運営委員会が必要とみとめたときには、臨時総会をひらくことができる。
7. 総会ではつぎのことを討議・決定する。
(ア) 年間の活動の成果の発表、つぎの活動の方針と計画
(イ) 予算と決算
(ウ) 役員の選出
(エ) そのほか、運営委員会がみとめたもの
8. 総会は会員の現在数の4分の1の出席で成立する。ただし、委任状で出席とみなすことができる。
9. 総会の議事は出席者の過半数で決する。
10. この会はつぎの役員をおき、役員の任期は2年とする。
① 運営委員 5名以上 ② 監事 1~2名
11. 運営委員は、立候補者、他薦者、各分科会と会報編集部と事務局の代表者が総会の前日までに運営委員会または事務局に申し出て、総会で決定する。また、年度途中でも運営委員が必要とみとめたら、あらたに増員することができる。
12. 運営委員会は、会を代表する。
13. 運営委員会は、運営委員長1名をおく。
14. 監事は、一年に一度、会務についての審査をおこなう。
15. 会計年度は一月一日から同年十二月三十一日とする。
16. この会則の変更は、総会の決議を経なければならない。
以上
〔内規〕
1,会費は、個人会員5000円、団体会員7000円とする。