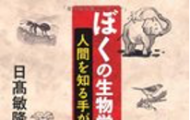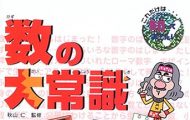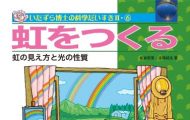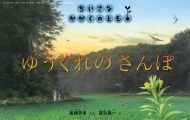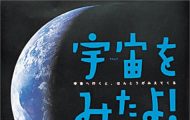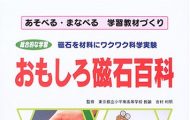| 1968.9 | 吉村証子宅で「科学読物を読む会」開催。参加者17名。 |
| 1968.10 | 会の名称を「科学読物研究会」とする。 |
| 1969.1 | 板倉聖宣を1月例会講師として、「科学読物研究会」の公式のスタート。 |
| 1969.7 | 年報第1号発行。会員13名。年会費240円。 |
| 1970.1 | 「科学読物を選ぶ資料」(定価40円)ができる。400冊の科学読物を分野別に配置したブックリスト。 |
| 1970.7 | 年報第2号、会員50名を越える。 |
| 1971 | 第一月曜に吉村宅で「新刊を読む会」はじまる。 |
| 1972.7 | 会員81名、年報第3号発行。年会費400円。 |
| 1973.4 | 当会と高井戸親子読書会共催 区立富士見丘小学校で例会 かこさとし氏出席。 |
| 1973.7 | 「科学読物を選ぶ資料」第2版発行。収録本は750冊。杉並区立柿の木図書館で科学あそび始まる。 |
| 1974 | 「学年別科学読物を選ぶ資料(小学校理科準拠)」発行。76年に増補。年会費500円。 |
| 1975.1 | 会報が月報となり年10回発行のスタイルになる。 |
| 1976.3 | 会員有志による訳書「わたしたちの環境科学」(文理書院)発行。 |
| 1977.8 | 「科学の本はむずかしくない-子どもと科学を結ぶ200選」発行。年会費1200円。 |
| 1978 | 「科学の本を使ってみたら」(日本教育科学研究所)発行。 |
| 1979.4 | 吉村証子没。 |
| 1980.1 | 「くらべ読み分科会」「科学論分科会」「新刊研究分科会」「科学遊び分科会」を発足させることに。 |
| 1980.1 | 「吉村証子記念文庫」の設立。年会費2000円。 |
| 1980.3 | 会報101号とする。「科学読物資料センター設置の要望」を杉並区立中央図書館に提出。 |
| 1980.3 | 京都科学読み物研究会発足。 |
| 1980.4 | 第一金曜日、渋谷の童話屋で「新刊研究会」スタート。「科学遊び分科会」スタート。 |
| 1981.1 | 会の規約案、役員人事と運営委員会制承認、会長に中川宏。年会費3000円。 |
| 1981.1 | 「教科書分科会」スタート。 |
| 1981 | 「吉村証子記念会」設立。「吉村証子記念日本科学読物賞」の制定。 |
| 1981.6.7 | 第1回吉村証子記念「日本科学読物賞」授賞式(東京都教育会館)。参加者100名超え。月刊科学絵本「かがくのとも」編集(福音館書店)受賞。 |
| 1981 | 「科学の本っておもしろい-子どもの世界を広げる250冊の本」(連合出版)発行。 |
| 熊本で科学読物研究会発足。 |
| 1982.12 | 杉並区立中央図書館の完成を機に、例会の会場を法政一高から中央図書館会議室に移す。 「吉村証子記念文庫」を中央図書館児童資料室に移管。 |
| 1983 | 中央図書館の依頼で、「科学あそび」の試演を始める。年会費3500円。 |
| 1983 | 大阪で「科学読物と理科の会」発足。 |
| 1985 | 「続科学の本っておもしろい」(連合出版)発行。 |
| 1987 | 会長に小峰光弘、会員数226 |
| 1987 | 「科学あそびだいすき」(連合出版)発行。年会費4000円。 |
| 1987.7 | 「親子で楽しむ博物館ガイド(首都圏版)」(大月書店)発行。 |
| 1989.2.11 | 「科学読物研究会の創立20周年を祝う会」(神楽坂エミール)参加者108名。年会費5000円。 |
| 1990.4 | 「しぜんかんさつ会」スタート |
| 『科学の本っておもしろい 第3集』出版 |
| 1991 | 「大阪科学読物研究会 第2回全国研究集会」 |
| 1993 | 『科学読物研究会二十年史』作成 |
| 『新版 親子で楽しむ博物館ガイド 首都圏版 1、2』出版 |
| 1994 | 会長に鈴木将。 |
| 1995 | 「全国研究集会 子どもと楽しむ自然と本」 『科学あそびだいすき 第2集』出版 |
| 1996 | 「全国研究集会 少年動物誌の舞台を訪ねて」 |
| 「日本科学読物賞」終了。 |
| 『科学の本っておもしろい 第4集』出版 |
| 『牛乳パックの実験』出版 |
| 1998.7.19~7.20 | 「30周年記念行事」開催。(国立教育会館) |
| 1998 | 『科学読物 データバンク98』出版 |
| 1999 | 「第5回全国研究集会」国立民族学博物館見学と科学読物研究集会 |
| 2001 | 「国際子ども図書館開館を考える会」入会。 |
| 2002 | 文部科学大臣賞受賞。 |
| メーリングリスト開始。 |
| 『科学あそびだいすき 第3集』出版 |
| 2003 | オーロラの会はじまる |
| 『新・科学の本っておもしろい』出版 |
| 2005 | ホームページ開設。 |
| 科学技術館メール マガジンに本の紹介文を掲載開始。 |
| 運営委員長 鈴木有子、個人会員235名、団体35。 |
| 2006 | サイエンスアゴラ始まり、参加。 |
| 2007 | 理科教室に本の紹介文を掲載開始。 |
| 2008 | 第1回科学読物シンポジウム参加。運営委員長 市川美代子。個人会員244名、団体39。 |
| 2008.12.6 | 40周年記念交流会(科学技術館)開催。『科学読物研究会創立40周年記念特集号』作成 |
| 2010 | 『科学の本っておもしろい2003-2009』出版 |
| 2011 | 会報400号 |
| 2018 | 会員個人240名 団体会員38 |
| 国立国際子ども図書館を考える会終了 |
| 『創立50周年記念特別号』作成 |
| 2018.10.28 | 50周年記念イベント「あつまれ!科学の本のなかまたち」(科学技術館)開催 |
| 2020 | 会報500号。会員個人220名 団体会員40。 |
| 2021.3 | 会員個人218名 団体会員42。 |